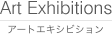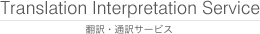2005年11月9日より7夜連続、7時間ずつに渡り、グッゲンハイム美術館にてマリーナ・アブラモビッチのパフォーマンス「Seven Easy Pieces」が行われた。これは、ローズリー・ゴールドバーグが運営する非営利団体「パフォーマ」が行う、世界初のパフォーマンス・アート・フェスティバルの一環として開かれたもので、様々なアーティストの、パフォーマンス史における代表的パフォーマンスを、アブラモビッチが再パフォーマンスするというイベントであった。またアブラモビッチは、これらのパフォーマンスを長年の親友であった、今は亡きスーザン・ソンタグへと捧げた。
第一夜 ブルース・ナウマン 「ボディー・プレッシャー」 初演 1974年
世界を変える象徴界・想像界の肥大化
第一夜は、ブルース・ナウマンが74年に行ったパフォーマンス「ボディ・プレッシャー」から始まった。この作品は、7つの作品の中で最もコンセプチャルな意味合いの強い作品である。
アブラモビッチは、グッゲンハイム・ミュージアムの中心に据えられたステージの上で、壁に見立てたガラスに、自らの身体を力強く押し付けていた。5分ほどのパフォーマンスを、午後5時から12時まで、ひたすら7時間に渡って繰り返し続けた。パフォーマンスを続けるアブラモビッチのシャツには、うっすらと汗がにじんでいた。
Marina Abramovic performing Bruce Nauman’s Body Pressure (1974) at the Solomon R. Guggenheim Museum on November 9, 2005.
Photograph by Kathryn Carr (c) The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York.
パフォーマンスが行われている間、彼女自身が吹き込んだ、こんな感じのアナウンスが流れている。ナウマンが当時発表した文章だ。
あなたの身体の前面を、できるだけ強く壁に押し付ける
手のひらの表、そして裏
右ほほ、または左ほほ
壁の厚さを忘れて
壁の向こう側で、(一歩前進したとして)あなた自身が自分の身体を押し返しているイメージを「想像」する
とても強く身体を押し付けて、そして押し付けているイメージそのものに集中する
壁の厚さを忘れて(壁を取り除け)
あなたの身体のどの部分が壁に触れているか考える
筋肉の緊張、痛み、そして匂いを考える
これはとてもエロティックなエクササイズになりえる
マリーナは、このパフォ−マンスを驚くべき集中力で続ける。にこりともしない。表情の崩れた瞬間は、一瞬たりともなかった。あたかも、今まで彼女が行ってきたパフォーマンス、そして彼女の身体の歴史性を物語っているかの様であった。
ナウマンが行ったこのパフォーマンスは、身体のイデア性に対するチャレンジの様に思える。鏡ではなく、人物が移りこまず、さらに向こう側の見えない壁を選んだ上で、パフォーマンスを行う。
ラカンは自己が知覚する世界を、想像界、象徴界、現実界との三つに分けて思考を開始したが、そのラカンは自己認識の段階を鏡像段階、すなわち鏡に映りこんだ自己の認識可能性から始めていた。このナウマンのパフォーマンスは、あたかも象徴界(シンボルの世界)、想像界(すなわちイメージの世界)、現実界(即物的なもの)を繋ぐボロメオの結び目をなぞるかの様である。世界を構成しているこの結び目は一つが切れてしまえば全てバラバラになってしまうものなのだが、ナウマンはその線の持つ多彩な位相をなぞっているかの様である。
ナウマンは大学院にて美術を専攻する前に数学と物理学を修めているが、”壁の向こう側で、あなた自身が自分の身体を押し返しているイメージを「想像」する”という下りは、数学的に見ても当然正しい。身体のバランスが崩れないのは、押されている壁が、押している身体を同等の力で押し返しているからである。
さらにここで、ナウマンは“とても強く身体を押し付けて、そして押し付けているイメージそのものに集中する”と、押し付けるという行為の持つイメージそのものを壁の向こうに想像しようとする。すなわち、存在そのものを「押し付けているイメージ=象徴」と「壁の向こうにある自らの身体=想像」と「壁=現実」という構造に分類している。さらにパフォーマンスを反復するという行為で、押すという行為の象徴性を肥大化させる。
ナウマンはこのパフォーマンスで、象徴と想像そのものを膨張させることにより、世界における現実、すなわち壁があるという現実そのものを打ち破ろうと試みているのである。すなわち、後に続く“壁の厚さを忘れて(壁を取り除け)”というラディカルな行為を、大真面目に試みているのだ。歴史的に見てみても、まさにパフォーマンスアートの代表的な作品と言える。
このパフォーマンスは一見無意味とも思えるかもしれないが、現実社会において貨幣が流通しているのは、貨幣という「象徴」、そして皆が疑いなく貨幣を使うであろうという「想像」の肥大化がもたらした世界であり、そこに現実(貨幣が持つファンダメンタル)は存在していない。という意味でも、このパフォーマンスは現在において十分な有効性を持ちえると言える。
Marina Abramovic performing Bruce Nauman’s Body Pressure (1974) at the Solomon R. Guggenheim Museum on November 9, 2005.
Photograph by Kathryn Carr (c) The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York.
ひたすら7時間に渡ってステージ上のガラス、さらにはステージの床へと自らの身体を押しつけ続けるアブラモビッチを見ていると、彼女の肉体が持っている歴史性を感じざるを得ない。数時間続くことによって見えてくる疲れ、そして汗、それは身体性以外のなにものでもない。
さらには人間の身体がもっている知覚そのものに関しても、感覚が鋭くなってくる。普段使わない、身体の異なる部分を使うことによって活性化してくる知覚を想像するだけでも、自己の感覚が研ぎ澄まされてくる。パフォーマンス中に客席から聞こえた携帯電話の着信音に対するとてつもない違和感は、ここから来ているのかもしれない。
しかし、このパフォーマンスはいくつかキュレートリアルな観点から見て残念な点が残った。グッゲンハイム美術館という大型の美術館でのパフォーマンスという事もあり、パフォーマンスがオーディエンスに見えやすいようにと、ステージ上に壁に見立てたガラスを使用しパフォーマンスを行った点である。「壁」という、その先が見えない「もの」ではなく、ガラスという透過性のある素材を使ってしまった為、ナウマンが対象としていた目の前にある即物的現実、さらには「想像」、を変化させてしまう結果となった。ナウマンの当初の意図が少しずれてしまい、当初のラディカルさが薄まってしまった印象を受けた。
第二夜 ビト・アコンチ 「シードベッド」 初演 1972年
自慰行為におけるイマジネーションと想定される他者
72年当時のパフォーマンスにおいて、アコンチは、ギャラリーの床に設置した傾斜の下に隠れ、ギャラリーを訪れた客を隠れ見ながら8時間、週3回に渡ってマスターベーションをし続けた。アコンチが出すあえぎ声はスピーカーを通じてギャラリーに流れ、観客はそれを鑑賞することになったのだが、それをアブラモビッチはグッゲンハイムでやってのけた。
Marina Abramovic performing performing Vito Acconci’s Seedbed (1972) at the Solomon R. Guggenheim Museum on November 10, 2005.
Photograph by Kathryn Carr (c) The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York.
今回のアブラモビッチによるパフォーマンスでは、円形のステージの下にアブラモビッチが隠れマスターベーションし続けた。アブラモビッチの出すあえぎ声は大型スピーカーによってミュージアム全体を包み込む。ミュ−ジアムに入った途端、その喘ぎ声の流れるミュージアムという空間の異様さにどぎまぎした。アブラモビッチの喘ぎ声が流れる空間では、グッゲンハイムの持つらせん状の展示スペースさえも淫靡な肉感を持つかのように見えた。
パフォーマンス中のアブラモビッチは、サービス精神が旺盛なのか、自分の妄想に関してずっとナレーションをしている。ohhhhh, yes, I love you….oh,oh, yes, I need you…I need your permanent erection…uunn..ohh..といった具合。そして、イク時にはちゃんとイク。ピークが来て、しばらくは落ち着くかな、と思っていたら、 darling, I am tired, I am going to peeといって放尿。しっかり音まで入るのだが、みんな苦笑していた。そして、数分も経たないうちに、また行為に入った。これを7時間、常時300人ほどいるオーディエンスの前で延々と行うのである。唖然としてしまった。
Marina Abramovic performing performing Vito Acconci’s Seedbed (1972) at the Solomon R. Guggenheim Museum on November 10, 2005.
Photograph by Kathryn Carr (c) The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York.
しかしここから考えられるのは、マスターベーションという自慰行為といえども、他者を想起せずに行うのは困難だという点である。いくらナルシストでも、自己を想起するだけでマスターベーションを成立させるのは不可能であろう。つまり自慰行為といえども、性交を前提としている行為を自己完結的に行っている時点で、他者性が必要となって来るのである。アコンチの場合、ギャラリーを訪れる人々を天井から隠れ見ながらマスターベーションを行ったが、マリーナの場合、密閉された空間にてパフォーマンスを行う為、聴衆とインタラクティブな関係を持つのは困難である。結果、他者をイメージして行為する必要があり、ただひたすら、自己の中にある他者性のみを膨らませてパフォーマンスし続けたのである。
私はこのパフォーマンスを見ている際、どうしてもユーゴスラビアという文脈におけるマスターベーションを使用した作品である、サンヤ・イベコビッチとの差異を考えてしまった。イベコビッチはチトーのパレードの日に、ザグレブにある自らのバルコニーで自慰行為の真似ごとをするのだが、その際、警察官から「バルコニーにものを置いてはいけない」という命令を受ける。ここにおけるイベコビッチの行為には、社会主義状況という文脈に置かれた女性の、痛烈な社会批判が感じられる。
アコンチは、ギャラリーという自慰行為がまず起こりえない場所(すなわちパブリックスペース)にて、あえて自慰行為を行うことによって擬似的プライベートスペースを作り出した。イベコビッチは、社会主義政権下に置かれた女性という立場を逆手にとり、一国の社会主義国の大統領のパレードの日における自分のアパートのベランダという、社会性と個人性を持つセミパブリックな空間において、スナイパーの真似事ではなく、マスターベーション(それは女性にとって武器と言える性的行為)によって、その輪郭をなぞろうとしたのである。
ちなみにイベコビッチによるこのパフォーマンスを男性が行った場合、完全に意味が変わってしまうだろう。女性が行うことによって、社会的文脈、すなわち大統領(男性、権力、垂直性))に対するイベコビッチ(女性、非権力、水平性)における強度が成立するのではないだろうか(近年の女性がヌードになって行う反戦運動も、文脈としては近いだろう)
アブラモビッチはアムステルダムの飾り窓にて行われた作品「ロール・エクスチェンジ」において、娼婦と自らの仕事を交換し、お互いの仕事(アーティスト=ギャラリーでのオープニング)(娼婦=売春行為)を完全にこなすというパフォーマンスを行っている。これは明らかにジェンダーに対する、アーティストとしての彼女なりの答えと言える。しかし、今回アブラモビッチが行った「seedbed」には、女性がこのパフォーマンスを行っているという悲痛さと滑稽さが同居していた。
さらに、アブラモビッチが行ったこのパフォーマンスにおいては、アコンチ的な意味合いよりも、マリーナ・アブラモビッチが行っているという象徴性、さらには神話性が前面に出ているように感じた。それはマリーナが自身を神格化しえている、というパフォーマンス・アーティストとしての最高の段階に到達している事によって成り立っていると言えよう。
第三夜 バリー・エクスポート 「アクション・パンツ:生殖パニック」 初演 1969年
公共スペースにおける女性と「見る/見られる」の関係
69年にバリー・エクスポートが行ったパフォーマンス「アクション・パンツ」は、自らが撮影した映画の上映会におけるパフォーマンスであった。エクスポートはポルノ映画の上映中、股間の開いたパンツを履いたまま聴衆の前に出て行き、「ここであなたが見ているのはリアリティ、つまりスクリーン上の出来事ではなく、そして皆はあなたがここを見ているのを見ています」というパフォーマンスであった。このパフォーマンスを、アブラモビッチは大胆に解釈して見せた。
Marina Abramovic performing VALIE EXPORT’s Action Pants: Genital Panic (1969) at the Solomon R. Guggenheim Museum on November 11, 2005.
Photograph by Kathryn Carr (c) The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York.
美術館に入ると、レザージャケットとブラックジーンズを履いたアブラモビッチが、マシンガンを持ったまま中央の椅子に座り、観客を睨み付けている。大柄なアブラモビッチがマシンガンを持って睨みつけていると、迫力満点なのだが、彼女の履いている黒いジーンスの股間の部分は完全に切り取られている。当たり前だが、股間が丸出しになっており、もちろん、そこからは陰毛と性器が露出している。聴衆は、必然的に彼女の股間に目が行ってしまう。
アブラモビッチはほとんどまばたきもせず、観客の方向を、マシンガンを抱えたまま7時間、驚くべき集中力を持って、ただひたすら見つめている。しかも、ただやみくもに観客の方に視線を投げかけているのではなく、観客の一人ひとりの目を凝視、もしくは睨みつけていくのである。アブラモビッチに睨まれた人達は、そのほぼ全員が、あまりのプレッシャーに耐えられず、目をそらしてしまう。アブラモビッチは時々立ったり座ったりを繰り返しながら、観客を監視し続ける。
しばらく待っていると、私の番が来た。アブラモビッチが私を睨む。私も彼女の目を睨み返す。私の首の筋肉が硬直していくのが分かる。アブラモビッチに睨まれて、緊張しているのだ。30秒ほど視線を交わし続けただろうか、その間、私は緊張しっぱなしだった。そして、やはり睨まれている間、股間に目をやる訳にはいかなかった。
Marina Abramovic performing VALIE EXPORT’s Action Pants: Genital Panic (1969) at the Solomon R. Guggenheim Museum on November 11, 2005.
Photograph by Kathryn Carr (c) The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York.
当たり前だが、股間を露出した女性を前にして、ほぼ全ての聴衆は彼女の股間に目をやる。しかし、アブラモビッチはマシンガンを持ったまま聴衆を監視し続けているので、彼女を見ようとする聴衆は、彼女に監視されていることになる。このマシンガンの重量感はなかなかのもので、銃を持った人間に監視されているかと思うと、おちおち彼女の股間に視線を投げやることはできない。ここでもアブラモビッチという大柄な女性が持つ「怖さ」のような、彼女自身が持つ神話的要素が強く働いている。
映画「プライベート・ライアン」において、戦場、すなわち公共スペースにおける二等兵(すなわちプライベート=私的?)という言語を利用して公共性の概念に批判的視点を投げかけたのはスピルバーグであったが、アブラモビッチもあくまで美術館という場にて性器を露出し、さらにイラク戦争を続ける米国の公共スペースにおいてマシンガンを持ち込んでパフォーマンスを行うことで、公共という概念に挑戦している様に思える。プライベートという言葉に見られる、ラテン語におけるpriという接頭語は「欠けた」という意味を持つ接頭語であり、ヘレニズム期においては否定的要素を持つ言葉であった。ローマ期にギリシャ語の語彙はラテン言語へと変換していったが、ローマ期以降のヘブライズム的記号的世界において、その意味合いはゆるやかに変わっていったと思われる。
ハンナ・アレントが、個人が成立することによって成立する公共性のもろさについて語っているように、アブラモビッチも公共性と個人の関係性の脆さに対して挑戦している様に思える。この文脈で捉えると、このパフォーマンスがスーザン・ソンタグに捧げられている事も納得が行く。
同時に、マシンガンを持ったまま監視を続ける彼女が、複数の警備員によって「監視」されていたのも興味深かった。これら警備員を抜きにして、彼女がパフォーマンスを行うことは困難である。美術館という場所において、美術品ではなくそこに集まる人達に焦点を当てて作品を作ったのはトーマス・シュトルートであったが、アブラモビッチの監視に関する作品は、美術館という場所において、いとも簡単に転倒してしまったのである。彼女の意図を抜きに、彼女の私的パフォーマンスは、公共における監視役によって守られたのである。
第四夜 ジーナ・ペイン 「コンディショニング 自画像における3つの段階における第一段階」 初演 1973年
美しいパフォーマンスをするということ
このパフォ−マンスにおいて、アブラモビッチは、25cmほどのろうそくの火が熱し続ける鉄製ベッドの上に横たわり、その熱さをひたすら耐えている。他の全てのパフォーマンスと同じく、これも7時間継続する。
Marina Abramovic performing Gina Pane’s Conditioning, first action of Self-Portraits (1973) at the Solomon R. Guggenheim Museum on November 12, 2005.
Photograph by Kathryn Carr c The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York.
ろうそくの火とベッドの間は10cmほどの間隔があり、見た目には熱いのかどうかは察しかねるのだが、時々小さく聞こえるうめき声で、アブラモビッチがかなりの高温に耐えているのである事が容易に想像できる。そして、約一時間おきにアブラモビッチは短くなったろうそくを自ら付け替え、またベッドへと横たわる。
印象的だったのは、ろうそくの火を付けかえる際に、アブラモビッチがベッドから起き上がるのではなく、ベッドから転落するようにドスンと落ちていた点である。あまりの音の大きさ、そして落ち方の不自然さに、観客一同、不安で一杯になってしまった。
他のパフォーマンスがかなり衝撃的だったのに対して、このパフォーマンスは比較的ビジュアル的に楽しめた。ゆらめく炎の上で横になっているアブラモビッチは、文句なしに美しかった。
第五夜 ヨーゼフ・ボイス 「死んだうさぎに写真をどう説明するか」 初演 1965年
新たなる神話の誕生 - civilizationとculture -
この作品は、今回のシリーズ中、最も批評が困難なパフォ−マンスではないだろうか。
ボイスのトレードマークであったフィッシャーマン・ベストを着たアブラモビッチは、顔中に金箔を貼り、足に張り付いた鉄のかかとをバシン、バシンと踏み鳴らしながらステージ上を歩き回る。ステージ上には片足にフェルトが巻きつけられた椅子、そしていくつかの黒いカンバスとイーゼル、そして死んだウサギが用意されている。
Marina Abramovic performing Joseph Bueys’s How to Explain Pictures to a Dead Hare (1965) at the Solomon R. Guggenheim Museum on November 13, 2005.
Photograph by Kathryn Carr (c) The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York.
死んだウサギは死後硬直の為か、身体が伸びきった形のまま、アブラモビッチにそっと抱かれている。ウサギを抱いたアブラモビッチはウサギを抱えたまま椅子に座り、そっと手を上に伸ばし、人差し指で天を指差す。死んだウサギは、もちろん死んでいるので、周囲で起こっている事態を把握できていない。それでもアブラモビッチは、ウサギを抱きかかえたまま、声には出さずにささやきかける。
その後アブラモビッチは、左手でウサギを抱えたまま用意された黒板の前に行くと、うさぎの手を人差し指で支え、その前でウサギの手を上下させる。その様は、非常に可愛らしい。今度はウサギの耳をくわえると、両手でウサギの手をもったままステージに這い蹲り、まるで生きたウサギが走っているかのように見立て、ステージ上を動き回る。それを何度も繰り返すのだが、ごくたまに、ステージ上につけられた床にあるふたを持ち上げ、穴の開いた床にステッキを入れてかきまぜる。あたかも日本書紀における列島誕生の際に、イザナキとイザナミが混沌の中に矛を刺し下ろし、こおろこおろと潮をかき鳴らすかの様に。ここから一つの答えを導くことが可能である。パフォーマンスはある種の神話の創造であるということである。
ヨーゼフ・ボイスは第二次世界大戦中、自らが操縦する戦闘機がクリミアに墜落した際タタール人に救済された経験が、自らの芸術活動に大きな影響を与えたと語っている。ここでのボイスの試みは、大戦を起こしてしまったヨーロッパの文化ではなく、その外部にある文化を、ヨーロッパの上位文化として位置づけようとするラディカルな行為であったと言える。もっと言ってしまえば、今まで下層として捉えられていた civilizationをcultureの上位に位置づけようとするラディカルな行為であったように思える。
ボイスが母国語としていたドイツ語において、Kultur(文化=culture)と Zivilisation(文明=civilization)は全く異なった意味を持っており、ドイツ語を話す人間は、明確にkultur=文化を上位に置き、Zivilisation=文明を下位に置いて思考している。この点で、ドイツ語話者は、その2つを明確に区別しないフランス語話者と英語話者とは異なった思考をしていると言える。
アブラモビッチの両親は対ドイツのパルチザン闘争におけるヒーローであった為、大げさに言ってしまえば第二次大戦当時ボイスとは敵対関係にあったと言える。アブラモビッチはアボリジニやチベットのラマとの修行を通じて、Zivilisationの偉大さを十分理解していることだろう。不思議とヨーロッパ近代の超克を試みる二人の芸術家がこういった形で交錯する様は、興奮を覚える。
混沌を全ての発生の場所と捉えたのは荘子であったが、それは数学的に見ても正しい。おそらくアジア的「混沌」は、このドイツ語的な思考においてはKultur(すなわち「カオス」)ではなく、Zivilization(「混沌」)に属するものであった。そういう点から見てみると、ボイスのパフォーマンスは、自然に対するヨーロッパ的視点の延長線上に位置づける必要がある様に思える。パフォーマンスという神話が、一神教的世界観の硬直性が招いたゆがみに対する反動として発生したのである。そして、当初このボイスのパフォーマンスは、大多数のヨーロッパ人にとって、当初は不可知で、気味の悪いものであったはずだ。しかし、大ミュージアムの中でパブリシティを持ちすぎた神話は、踊り念仏的なポップさを獲得してしまい、気味の悪さが抜けてしまっている。しかし、それはパフォーマンスそのものの失敗ではなく、時代を経た後のre-performanceの成果であると言えよう。
アブラモビッチには、何度となく死んだウサギにあえて語りかけることによって、会話の不可能性を飛躍する神話を創造しようと試みたが、週末の観客でごった返すグッゲンハイムという環境におけるパフォーマンスは、パフォーマーを神格化しがたい状況にあった。あまりの聴衆の多さに、パフォーマンスを集中して見ることが出来る環境ではなかったのである。象徴性を帯びるはずであった、鉄のかかとが打ち鳴らす音、それはあたかも空間に母音という発火点を与え、それを豊かに広げていくようなまさにZivilization的効果があったはずに違いないが、携帯電話の着信音というあまりにもKulturな音でかき消されるそれは、時代を超えたre-performanceの悲劇であったとしか言いようがない。その為、皮肉なことに、パフォーマンスの記録写真の方が神格化したアウラを持ちえるという状況が生まれてしまった。アブラモビッチの顔についた金箔がひらひらとする瞬間を捉えた写真は、きっと美しいだろう。しかし、ボイスのパフォーマンスにおいても、パフォーマンスを記録したビデオより写真の方がドラマチックに見えるのは、記録媒体が伝える情報の悲劇としか言いようが無い。
第六夜 マリーナ・アブラモビッチ 「リップス・オブ・トマス」 初演1975年
赤い星の下に生まれたアーティストの運命とスラブ民族の悲劇
第六夜。この日は彼女自身が75年に行った伝説的パフォーマンス「リップス・オブ・トマス」のre-performanceの日である。このパフォーマンスは彼女がユーゴスラビアを去った直後の75年にドイツのインスブルックで行われたパフォーマンスであり、ユーゴを背負ったアブラモビッチの思いが見え隠れする作品である。
Marina Abramovic
Performance still from Lips of Thomas, 1975.
Performance, Galerie Krinzinger, Innsbruck.
Photo courtesy of the artist and Sean Kelly Gallery, New York.
c 2005 Artists Rights Society (ARS), NY/VG Bild-Kunst, Bonn.
午後5時ちょうど、いきなりステージにアブラモビッチが一糸まとわぬ姿で現れると、椅子に座り、テーブルの上にあったメトロノームの電源を入れ、しばらくそのまま座った。ゆっくりと、メトロノームのカチ、カチ、という金属音のみが会場に響き渡る。10分ほど経ったのち、アブラモビッチは1リットルのハチミツが入った瓶の蓋を開け、スプーンを瓶に出し入れしながらゆっくり、ゆっくりとハチミツを食べていく。何度も何度もスプーンを舐める様は、非常に性的であった。
10分ほどハチミツを食べた後、今度はワインの蓋を空け、客の方向をじっと見つめたまま、ゆっくりと飲む。そして、テーブルの上にあったカミソリを手にすると、裸のままステージの前方に立ち、お腹の上にあらかじめ書かれていた星の上を、丁寧になぞるようにゆっくりと切っていく。その間、メトロノームの音が、ゆっくりと時を刻んでいく。
切り傷からは血がゆっくりと滴っていく。アブラモビッチはその血を白いナプキンで拭き取った後、ステージ上に置いてあった古ぼけた軍靴を履き、さらに軍帽をかぶり、ステッキを持つ。軍帽には赤い星が付いており、ゆるやかなカーブを描いたステッキの方は、それだけであたかもカラシニコフ銃を持っているかの様な印象を観客に与える。(マリーナ本人が私に語ってくれた所によると、この靴とステッキは1988年に行われたパフォーマンス「The Lovers ? Great Wall Walk」に使われたもので、ステッキはパフォーマンス後15cmも短くなっていたそうです。)しばらく直立不動のままでいると、スピーカーから、女性の声でロシア語の歌が流れてきた。その歌はスラブの悲劇を歌った民謡なのだが、こんな歌詞であった。
おお神よ、我らが民を守りたまえ
その名にご加護を
我を許したまえ 神よ 我らの罪を
地球上で犯された罪を
我らを見給え スラブの魂よ
世界中で苦しむその魂よ
誰も我を理解せず
我の運命は一銭にも足らず
・・・
戦いは我らの永遠の十字架
我らがスラブよ 生き延びたまえ
驚いたのは、この歌が流れた途端、アブラモビッチは声をあげ、そして大粒の涙を流しながら号泣したことだ。腹部から血を流している一糸まとわぬ女性が号泣している様は、まさに異様であった。
歌が流れ終わった後、アブラモビッチは靴を脱ぐと、今度は十字架状に配置された氷のベッドの上に裸のまま横たわった。五分ほど氷の上に横たわった後、今度は鞭で自らの背中を、声を上げながら繰り返し激しく打ち付けた。
この一連のパフォーマンスを、アブラモビッチは7時間に渡って繰り返し行った。3時間目くらいだったろうか、腹部を星型に切った後、その血をぬぐった白いハンカチを広げると、それには紐がついており、アブラモビッチはその紐の端を、棒の切れ端に結びつけた。あのロシア語の歌が流れた際、アブラモビッチは血のりのついた白いハンカチが結ばれた棒を持ち上げると、それを大きく振った。あたかも、彼女が何かに「降伏」しているかの様に。この時、アブラモビッチはもう涙を流しておらず、うっすらと笑顔さえ浮かべていた。
午後11時くらいになった時だろうか、氷のベッドから起き上がったアブラモビッチの震えが止まらない。体温が奪われたせいか、小刻みに身体が震えたまま、立っていられない様な状態なのだ。もう、見ていられない。75年初演当時、もう見ていられない、と思い飛び込んできた観客がパフォーマンスを終了させたのだが、今回も会場から「もうたくさんだ」「お願いだからもうやめて」という声が飛び交った。しかし、それでもアブラモビッチはパフォーマンスを辞めなかった。
Marina Abramovic
Performance still from Lips of Thomas, 1975.
Performance, Galerie Krinzinger, Innsbruck.
Photo courtesy of the artist and Sean Kelly Gallery, New York.
c 2005 Artists Rights Society (ARS), NY/VG Bild-Kunst, Bonn.
Marina Abramovic
performing Lips of Thomas (1975) at the Solomon R. Guggenheim Museum on November 14, 2005. Photograph by Kathryn Carr (c)
The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York.
そんな中、アブラモビッチはますます激しく自らの身体を鞭打つ。アブラモビッチは鞭打つ度、ますます声を大きく上げる。さらに身体の感覚が麻痺してきたのだろうか、氷の上に横たわっている時間がだんだんと長くなってきた。
一体、このパフォーマンスは何を意味しているのであろうか?ナンセンスと思われるのを承知で、あえて解釈を試みてみたい。
マリーナ・アブラモビッチの両親は対ドイツパルチザンのヒーローでありチトーの側近である。またアブラモビッチの母方の祖父は東方正教会の大司教であり、ローマ・カトリックとの融和を拒んだ為、王族に毒殺され、それがきっかけでアブラモビッチの母親は共産党に入党したと、彼女自身著書の中で述べている。展示中、たまたまグッゲンハイムにて「Russia!」展が開かれており、その展示を見ながら感じたのは、スラブ圏におけるローマ、すなわちラテンの影響である。
例えばロシアの皇帝の呼称ツァーリ(英語だとTsar)は、ビザンツ時代の公用語であるギリシア語のカイサルから来たものである。スラブという言葉はギリシア語を通じて世界に広がったが、ギリシア語圏がビザンツ帝国に取り込まれた際、戦争に負けていたスラブ人は奴隷、すなわちスレイブとなり、その後英語のslaveに見られるように隷属する民族、つまりスラブ民族となった歴史がある。それがラテン語に直接取り込まれ、英語にも名残を残しているのである。19世紀になり諸国民の春において民族覚醒が起こると、続くロシア革命に続く汎スラブ主義が台頭し、ユーゴスラビア、すなわち南スラブ人連邦共和国の創造に繋がっていく。しかしそれも共産主義崩壊の煽りを受け内戦に陥り、最終的に共産圏包囲網の軍隊であった NATOによる空爆を招くことになった。
Marina Abramovic
Performance still from Lips of Thomas, 1975.
Performance, Galerie Krinzinger, Innsbruck.
Photo courtesy of the artist and Sean Kelly Gallery, New York.
c 2005 Artists Rights Society (ARS), NY/VG Bild-Kunst, Bonn.
自らの身体を打ち付けるという行為は、このスレイブとしての民族的ルサンチマンを背負ってしまった彼女が行う、必死の叫びにも似た表現なのかもしれない。東方正教会のシンボルである十字架を氷で作るという行為が、スラブのルーツの一つであるロシアを彷彿とさせる。
スラブの悲劇を物語るロシア語の歌は、戦争の歴史、さらにはユーゴスラビア解体の悲劇の歴史以外の何者でもないのではないか。そもそも彼女の祖父の殺害と母親の共産党入党、さらに西ヨーロッパ亡命後のユーゴ内戦を外部から見るという経緯そのものが、90年代のユーゴスラビア解体の悲劇と直結する。(クロアチア人とセルビア人の違いは同じスラブ民族における、ローマ・カトリックと東方正教会という宗教の違いであり、それが90年代のユーゴ紛争の最大の問題である)
Marina Abramovic
Performance still from Lips of Thomas, 1975.
Performance, Galerie Krinzinger, Innsbruck.
Photo courtesy of the artist and Sean Kelly Gallery, New York.
c 2005 Artists Rights Society (ARS), NY/VG Bild-Kunst, Bonn.
そして、このパフォーマンスそのものがスーザン・ソンタグに捧げられているのは、アブラモビッチがソンタグの人柄やマルチカルチュラルな視点に敬意を表しているのみならず、ソンタグが行った「Waiting for Godot in Sarajevo」に触発されたアブラモビッチなりの美的表現にほかならないのではないか。お腹の中にいる時から共産主義の名の下に生まれることを運命づけられたマリーナ・アブラモビッチ。カミソリで腹部を切り取り、自らの血でRed Starを描き、さらにそのRed Starから流れる血で染められた白旗をNATOの宗主国アメリカにてかかげた彼女は、あたかも国家の象徴ブリタニカやマリアンヌの如く、ユーゴスラビアを背負ったマリーナ・アブラモビッチその人ではなかったか。
なお、75年当時、他者が彼女の痛みを想像するに耐えられないと思った瞬間、彼女のパフォーマンスが終了したのだが、それもやはり他者性に回帰する。パレート効率が成立するのは、他者が自己の中に成立しえた場合である。それはカント的に言えば、他者を手段ではなく目的とせよ、という事であり、社会的に言えば、外部不経済を内部化することになる。それを自己管理社会主義という構造において行おうとしたのが、ユーゴスラビアであった。
またBalkanという言葉はトルコ語で「血とハチミツ」と読むことが可能である。パフォーマンス冒頭にて現れるハチミツとワインは、彼女の文化的背景を物語っているかのようであった。
さらにロシア語の歌を聴いた後私の頭によぎったのは、一人ぼっちという感覚である。体制のゆがみに最も敏感な人間が、それに対する批判ゆえに、祖国を離れることはよくある事である。ジャン・ファンは中国の体制批判的な作品を作る際、自己虐待的な作品を作ったが、アブラモビッチもそうではなかったか。アブラモビッチは文化的、政治的理由で祖国を離れたが(アブラモビッチ自身が私に、ユーゴスラビア外部の芸術に影響を与えたかったと話してくれた)その彼女に、祖国はもうない。裸のまま軍帽を被り、遠くを見つめたまま直立するアブラモビッチと、オーディエンス、すなわちアメリカの現実会との乖離が著しく、それが興味深くもあった。
また、前回のボイスのパフォーマンスとは打って変って、観客のほぼ全員が静かに見入っていたのが印象的であった。この日のパフォーマンスは、マリーナのステージの背中側に目隠し状の壁を用意したことにより、パフォーマーの神格化が置きやすい状況が作れたと思う。また、パフォーマーが裸体で行っているというのが、通常でない雰囲気を作るには十分だったのかもしれない。このパフォーマンスにおいて、アブラモビッチは自らを神格化しえたと言えるのではないか。
深夜12時、パフォーマンスが終了すると、会場は割れんばかりの拍手に包まれた。涙を流している女性客が多かったのが印象的だった。7時間一緒に時間を共有した私にも感動が湧き上がり、涙がこぼれそうになった。
第七夜 他の世界への侵入Entering the other side 新作:初演 2005年
「あなた」 と 「わたし」 が 「ここ」 にいるということ
パフォーマンス最終日の第7夜。まず会場に入った際、巨大なインスタレーションに度肝を抜かれた。ヨウジ・ヤマモトの3mのスカートドレスを彷彿とさせる巨大なドレスを着た(またはその上に立った)アブラモビッチが、グッゲンハイムの中心に置かれたステージの上に位置し、周囲を見回していた。これがアブラモビッチの新作であるが、今までの作品の中ではグッゲンハイムのスペースを最も有効に利用した作品ではないだろうか。
Marina Abramovic performing Entering the Other Side (2005) at the Solomon R. Guggenheim Museum on November 15, 2005.
Photograph by Kathryn Carr (c) The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York.
その巨大なドレスには異なった青色のストライプが螺旋状に伸びており、綺麗だった。そのドレスの上部に鎮座したアブラモビッチは両手を広げたまま、その角度を幾度となく変えつつ上半身をひねりながらただひたすら四方を見回していた。その行為には迫力があり、手を地面に向けると、あたかも地霊に向かって何かを呼び起こしているかの様である。また手を天に向けて祈るような仕種は、消費されない「祈り」という行為を追求しているかの様であった。
現在の記号化された世界では、全ては消費の対象となりかねない。記号化されない言語によって語るのが批評家の仕事であるのならば、記号化されず、消費されない「祈り」という行為を創造するのがパフォーマンス・アーティストの仕事の一つとも言えるかもしれない。それが成立した時に、そのパフォーマンスは神話として成立し得るのである。
祈りを捧げるという行為は一見無意味だが、到達しえないものに対して、つまり不可能性に対して絶対的なエネルギーを注ぐのが「祈り」という真摯な行為なのではないか。掛け替えの無さ、そこに全精力を捧げること、そこに価値があるのではないか。
あたかも鳥のように手を広げてパフォーマンスを続けるアブラモビッチの吐息はマイクによって拾われ、聞こえるか聞こえないかの音量で会場に流れている。比嘉豊光氏の映画「ナナムイ」は、宮古島における儀式、すなわち50代を過ぎた女性が山にある神社に集い、神の為に歌い踊った後に鳥になって空に飛んでいくという儀式を捉えていたが、アブラモビッチのこのパフォーマンスも、形さえ違えども、その様な女性の身体性を表出していたのではないかと思える。つまり、ある一定の年齢を超えた女性の身体のみが持つ、特有の反応があったのではないだろうか。
パフォーマンス終了が近づいた11時55分、アブラモビッチがこうささやいた。
Please close your eye, please.
そして彼女はこう続けた。
Imagine.
I am here, and now.
You are here, and now.
There is no time.
あなたがここにいる、ということ、そして私がここにいて、一緒の時間を過ごしているという事は、奇跡的なことである。時間と空間のゆがみが引力であり、それを共有した世界を私達は暮らしているのである。
しかし、現代美術の構造そのものが新興宗教と似ているという状況もあり、その点には批判的である必要があるのではないか。ゆえに、この新作は手放しで評価できるものではないと私は考える。コンセプト的には非常に60年代的で素直に美しいものかもしれないが、そういった作品を受け入れる状況が現代に無いのかもしれない。それは非常に残念なものではあるが、時代に合わせて新しいものを作っているのも重要かもしれない。
このパフォーマンスが終わった後、会場は途切れることのない拍手が沸き起こった。衣装を着替えたアブラモビッチは、関係者の方々にhugをした後、私も含めた観客の一人ひとりと抱擁を交わした。その気さくさは、非常に彼女らしい行為だったように思える。
そう、I am here now, and you are here now.そういうことである。
(C)Copyright Shinya Watanabe
Shinya Watanabe is a member of the National Press Association in the United States.