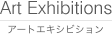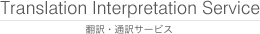渡辺真也
「自分らしく、自分だけの生き方のルールを見つけること。」簡単な問いではあるが、皆が思い悩むことではないか。私自身も思春期から今に至るまで、それを見つけようと努力してきた様に思う。
この問いが暇と退屈の問題だと気付かなかった私は、答えを見つけるべく、がむしゃらに生きて来た。しかし哲学者である國分功一朗氏は、この問いが暇と退屈にどう向き合うのかという人類普遍の問題であることを指摘し、本書ではこの問いをたてた等身大の自己に向かい合いながら、この答えを見つけて行こうと試みている。
この本は人生論であり、人生の本質をつかむ為の啓蒙書である。にもかかわらず、哲学書としては異例と言って良いほど読み易く、読み進めて行くうちに、あたかも著者と一緒にこの問題を考えているかの様な錯覚に捕われる。「自分らしく、自分だけの生き方のルールを見つけること。」その為にはどうしたら良いのだろう?と思い悩む全ての人、そしてできれば大学生くらいの若者に是非お勧めしたい本である。
冒頭、著者はホルクハイマーとアドルノによる、消費者の感性が制作に先取りされているという、大衆社会における暇の搾取の視点から消費社会を批判しながら、暇と退屈という普遍的なテーマを、哲学者たちによる豊富な文献に当たりながら、分かり易く掘り下げて行く。
第二章では、退屈の発生の起源について、人類が約1万年前に始めた「定住革命」という視点から、経済格差や権力関係の発生などの近代化に伴う暇の問題を探っている。第三章と第四章では消費と労働、そして疎外について考察し、第五章では、この本の白眉であるハイデガーの退屈論を丁寧に考察して行く。第六章では、動物たち一つ一つの世界というユクスキュルの環世界の議論を用いながら人間と動物の違いを述べ、七章ではコジューブの言う「歴史の終わり」や「動物」としての人間の議論を、「壮大な勘違い」として批判的に考察する。
この本の特徴の一つとして、脚注がとても良く書かれている点が挙げられる。アレントによる、マルクスの労働に関する悪質な読み替えの箇所など、原書を引いて丁寧に立証している(アレントはおそらく、ドイツ語が詠めない英語読者を想定してこの文を書いたか、もしくは英語の思考に彼女が引っ張られてしまったのだろう)。さらに、ノヴァーリスに対するハイデガーの理解が不十分であった点(後述)を、細かな脚注を通じて指摘しており、見事な出来映えだった。これにより本書で議論されている哲学者たちの原書に当たることが可能となっており、多くの人に開かれたアカデミックな哲学書に仕上がっている。
定住革命と芸術生産に関して考える
本書全体を通読してみて、私には定住革命の箇所、そして「動物」の議論がとても興味深かった。
西田正規の提唱する定住革命とは、人類は約1万年前に、中緯度帯で遊動生活から定住生活に移ったことを指す。ちなみに日本では約1万年前まで遊動生活を行っており、この頃から縄文時代が始まった。この定住革命が遊牧とは異なる権力関係の変化をもたらし、さらには退屈を回避する必要性を生み出したと述べられている。
また、本書の発刊記念トーク「〈人間であること〉」にて千葉雅也氏が、人間は動物と比較すると、友愛的な感心をより多くに向けてしまう、という動物行動学者であるドミニク・レステル氏の言葉を引いていた。そこから、ユクスキュルの環世界を「友愛」として捉えてみると、芸術生産という視点から、とても興味深いことが考えられる。
ニューヨークにて「時の番人」を務めるアーティストから、人類最古の洞窟画のお話を伺ったことがある。彼は、約15,000年前の旧石器時代後期のクロマニョン人(新人)によって描かれたラスコーやアルタミラの洞窟壁画は、動物たちが狩りの対象として描かれているが、世界最古の壁画と考えられている、ネアンデルタール人(旧人)により約3万年前に描かれたショーヴェ洞窟壁画を見た際、動物たちが友愛の対象として描かれていると感じたと言う。彼は、この頃の旧人はきっと個体数が少なく、動物を狩らずに、その死骸を食べるだけで十分に生活が可能だったのではないか、と推測してした。
國分氏が述べる様に、退屈の起源は歴史学によっては答えを出せないものの、ネアンデルタール人がたまたま考案した「描く」という行為がショーヴェ洞窟にて誕生し、その後のクロマニョン人たちは定住を始め、狩りをすることで生産性が向上し、「暇つぶし」として描かれたのが、ラスコーとアルタミラの洞窟壁画だった、と考えることは可能ではないか。これは、旧人から新人、そしてホモ・サピエンスへと、人類が一歩一歩進化して行った歩みに他ならない。
ネアンデルタール人によりショーヴェ洞窟壁画が描かれたのは約3万年前、ちょうど地殻変動により日本列島がユーラシア大陸から分裂した頃と一致する。また、ナショナルジオグラフィック誌が報じた最近の研究によると、ネアンデルタール人は約3万年前、ホモサピエンス(現世人類、つまり私たち)との交配により消滅した可能性が高いと言う。
(ちなみに私は、約4500~3200年前に富士山頂から噴き出していた溶岩が、日本列島におけるフォッサマグナ以北を地理的に分断し、その結果ユーラシア大陸から日本本島西方へと広がった弥生文化の北部への流入が遅れたため、北部に縄文文化が取り残された、という仮説を、Volcano Lovers展のキュレートリアル・ステートメントにて述べた。)
この視点から俯瞰すると、動物を友愛の対象として描いた、まだ言葉を話すことができなかったネアンデルタール人による壁画と、「言」と「事」が同一の概念だった日本語の空間との間に、補助線を引くことが可能となる。
万葉の歌人である柿本人麻呂は、山に遮られた、故郷に残してきた妻の姿を見たい一心で、
偲(しの)ふらん 妹が門見む 靡(なび)けこの山
という句を、山に向かって詠んだ。柿本人麻呂は、「言」葉による物「事」の変化を起こすべく、言霊を通じて、人間にではなく、自然へと語りかけることで、山を靡かせようと試みた。つまり、この頃の日本人は、自我が自然から切り離されておらず、自然が支配の対象ではなく、自らが放つ言葉と表裏一体になった、友愛の対象として認識されていたのだろう、と想像することができる。
環世界、世界の終わりと動物化
國分氏は、人間は環世界移動能力が高いため、何か特定の対象に<とりさらわれ>続けることができない、つまり動物の様に一つの環世界にひたることができず、退屈に悩まされてしまう、と述べている。
環世界移動という考え方は、インターナショナリズムやユニヴァーサリズムへと繋がるノヴァーリスのロマン主義とも親和性が高い。すなわち、(a)人間にとっての環世界と(b)犬にとっての環世界、(a)自己と(b)環境/自然、(a)自国と(b)他国など、ある種のパレーシア状態を目指したモダニズムの枠組みにおける他者論として置き換えることが可能であり、このノヴァーリスの思想がナポレオン戦争下にナショナリズムを説いた観念論者フィヒテの影響下に花開いたことは興味深い。國分氏はノヴァーリスの言葉「哲学とはほんらい郷愁であり、どこにいても家に居るように居たいと願うひとつの衝動である」を、哲学はどこに行っても通用する概念であり、故に哲学にとってはいかなる土地もふるさとになる、と読み解き、ハイデガーは、ノヴァーリスの言う郷愁に含まれる「いかなる土地もふるさとである」という要素が十分に理解していないのでは、と指摘している点は見事である。
さらに國分氏は、ハイデガーが人間に環世界を認めなかったのは、ハイデガーが人間は特別であると信念を抱いていたからだと指摘している。私はこのハイデガーの信念の背景に、ギリシャ語に起源を持つホモ・サピエンス(英知人)という言葉や、キリスト教の世界観が持つ固定観念が強く影響している様に感じられる。
また、本書で議論されている「世界の終わり」は、隣国フランスのナポレオンがイエナに入城する際、「世界精神が馬に乗って通る」と語ったヘーゲルによって打ち立てられた。その「世界の終わり」を再演したロシア人であるコジューブの日本に対する幻想は、日露戦争で父を失った彼が、特攻やハラキリというテーマを特別視してしまったのではないか、と私には思える。
國分氏は、コジューブの「歴史の終わり」や「人間の動物化」の議論を壮大な勘違いだと指摘し、逃げ込んだ人間を勝手に理想化しただけだ、と批判しており、私も同感する。しかし私は、本書にて述べられている「動物」の概念、すなわち(1)ユクスキュルが述べる環世界を生きる実際の「動物」、(2)ハイデガーが考えていた衝動の停止と解除だけでしか行動できない「動物」、(3)コジューブが述べている<歴史以後>に幸福を追求せず、ただひたすら満足に浸るメタファーとしての「動物」、また國分氏が引く(4)ドゥルーズの「待ち構える」という言葉が、<動物になること>が発生する瞬間を待つと想定した場合に想定される「動物」、(5)環世界において何らかの対象にとりさらわれている「動物」の5つの分類が少し未整理な印象を受けた。<動物になること>について話す際、この違いを整理して、クリアに述べる必要があった様に感じた。
7章の終わりにある「人間には人間的な生から抜け出す可能性、<動物になること>の可能性がある」という言葉は、前向きなハイデガー批判として書かれたものだと考えられる。ハイデガーによる「なんとなく退屈だ」という問いは、存在や問いが曖昧なだけに、解決方法を見つけるのが極めて困難な問いだ。つまり、選択の自由が主体的に残されたことが、この「なんとなく退屈」な状態を生み出しているのだから、その問いに対する明確な回答をする術を持つことは困難である。
結論の三つ目に、國分氏は「人が退屈を逃れるのは、人間らしい生活からはずれた時である、と。そして、動物が一つの環世界にひたっている高い能力を持ち、何らかの対象にとりさらわれていることがしばしばであるのなら、その状態は<動物になること>と称することができよう。」
「<動物になること>という第三の結論は、<人間であること>を楽しむことという第二の結論を、その前提としていることが分かるのである。」
「<人間であること>を楽しむことで、<動物になること>を待ち構えることができるようになる。」
と結論づけている。
人間は高い環世界移動能力を持っているため、何か特定の対象に<とりさらわれ>続けることができない、つまり動物とは異なり、人間は一つの環世界にひたることができず、退屈に悩まされてしまうのだとした場合、人間であることを楽しみながら<動物になること>が、果たして本当に正しい結論なのか、疑問に感じた。人が退屈を逃れることと<動物になること>は、かなり慎重に論じる必要があるだろう。
<動物になること>とは?
もし仮に、<動物になること>が結論だとすると、ここで言う<動物になること>は、環世界における環世界移動能力を持たない動物の様に、何らかの対象にとりさらわれたかの様に「熱中する」という意味であり、上記の分類の(4)ドゥルーズの「待ち構える」という言葉が、<動物になること>が発生する瞬間を待つと想定した場合に想定される「動物」と、(5)環世界において何らかの対象にとりさらわれている「動物」に相当する。
つまり、(1)ユクスキュルが述べる環世界を生きる実際の「動物」になる訳でも、(2)ハイデガーが考えていた衝動の停止と解除だけでしか行動できない「動物」になる訳でも、(3)コジューブが述べている<歴史以後>に幸福を追求せず、ただひたすら満足に浸るメタファーとしての「動物」になる訳でもない。つまり重要なのは、環世界を移動して「動物」の世界を体験することではなく、<動物になること>、つまり動物の様に熱中することなのだ。
しかし、退屈を逃れるために<動物になること>が、環世界を移動して動物の世界を体験することではないとするのであれば、高い環世界間の移動能力を前景化したノヴァーリスを引いて、ロマン主義的なユニヴァーサリズムや他者理解的要素に対するハイデガーの理解が不十分だったと批判した立脚点は、退屈を逃れるために<動物になること>を選択すると同時に消滅してしまう恐れがある。
この<動物になる>という言葉が、どうも私には、しっくり来ない。その理由の一つには、私達が生まれ育った現代日本が、<動物になること>を実践することでもたらされた悲劇を体験してしまっているからだ。
オウム真理教の教義に取り入れられたチベット密教ニンマ派の修行では、人間が動物になる修行が含まれており、その中にはマスターベーションをすることで人間が動物となって解脱する、と言う修行があったと言う。ニンマ派は人類最古の文化と考えられているボン教の教えから派生したものだと言われており、これは約1万年前、すなわちネアンデルタール人がホモサピエンスとの交配により消滅した後、定住革命が起こった時期とほぼ一致している。
つまり、<人間であること>を楽しむことができた1万年前のホモサピエンスは、猿になる儀式を行う、すなわち<動物になること>を儀式化したことで<人間であること>を確認できたと考えると、もしも現代日本人が<人間であること>を楽しみながら<動物になること>の実践の一つが、オウム事件を引き起こしたと考えられるのではないか。だからこそ私は、<動物になること>の持つ意味について、慎重に考えざるを得ない。
國分氏と千葉氏のトークを見ていて、彼らのハイデガー批判の根底には、ハイデガーの言う「なんとなく退屈だ」のactiveな解決方法がファシズムを引き起こしてしまう可能性があることを前提にしていると私は考える。しかし、実際に修行を通じて<人間であること>から<動物になること>を実践してしまい、新たな環世界に浸ることで退屈を克服したであろう人間たちが、日本で地下鉄サリン事件を起こしてしまったことに対しても、批判的に考察する必要がある。(日本はオウム事件を究極的なレベルで反省し、乗り越えることができたと言えるのだろうか。そこには日本という消費社会における「疎外」の問題が大きく横たわっているが、オウム裁判の終焉と同時に、全てが曖昧になってしまう気がしてならない。)
<動物になること>と仮想世界について
ここでいくつか動物の例を挙げて、退屈について、そして<動物になること>について、私なりに考察してみたい。
ここに、一匹の猫がいる。この猫は、ネズミの住む穴の前で獲物を待ち構えている。この猫は、果たして退屈か。
この獲物を「待ち構える(まさにドゥルーズの言った言葉!)」猫には、近い未来、ネズミが出入りするという予想が働いており、このネズミを食べれば満腹になれる、という期待が働いている。つまりこの猫は、近い未来に獲物が通るだろう、という仮想領域を含む環世界に「とりさらわれて」おり、退屈はしていない。
先日ベルリン市街で、とあるカラスを見た。このカラスは、トラックが道を通過する直前、自分がくわえているくるみをトラックの前に落下させ、そのタイヤに潰させたくるみを食べていた。同じことをしているカラスに日本でも出会ったことがあるが、これらのカラスは、トラックの進行方向やその時間軸、タイヤがクルミを砕くというイメージなど、仮想領域を思い描いた環世界に生きていることが分かる。
また仮に私が、「今から指パッチンするから見てて」とあなたに言ったとしよう。その後、私が指パッチンをするまで(それは1秒から10秒くらいの短い間だろう)、指パッチンをする私を思い描いているあなたは、未来に起こるであろう私の指パッチンを思い描くことに「とりさらわれて」しまい、その間、退屈については全く考慮する余地は無いだろう。
すると、退屈を逃れるために、「何らかの対象にとりさらわれる」こと、すなわち狭義における<動物になること>の中には、環世界の内部における、未来への期待という仮想領域が含まれることになる。
つまり、ハイデガーの言う「なんとなく退屈だ」という状態は、仮想領域の欠如である。つまりハイデガーは、退屈から逃れるためには仮想領域を拡大する必要があり、それは決断によって自らの可能性を実現することである、と述べているのではないか。仮想や希望を持つことはワクワクすることであり、これなら退屈を駆逐できるだろう。
すると、ここにパラドクスが発生する。<動物になること>の中に、ハイデガーが「人間だけ」が可能だと考えられてきた仮想領域を想定する必要が出て来るのである。つまり、猫やカラスも人間と同じく実存を生きているというパラドクスが発生し、仮想の領域をコギトとしてキリスト教神学の中で固定化したデカルト的世界観が破綻してしまう。さらにこの仮想領域は、考える自己を存在として位置づけるフィクション(仮想)から成立するデカルト的世界観の中でのみ定量化可能であり、これは矛盾を内包することで発生することが可能となる。
このキリスト教神学に根ざした存在や仮想の脱領域化を試みたのが、並行論を生み出した汎神論者であるスピノザであったとするのであれば、彼の汎神論の中に仮想の問題を位置づけ、人間と動物の環世界と暇について論じることはできないだろうか?例えばスピノザは、希望とは我々がその結果について疑っている未来または過去の物の表象像から生ずる不確かな喜びにほかならない、そして希望のない不安はあり得ないし、不安のない希望というのもあり得ないと述べている。これは未来という仮想についてスピノザ的に考えるヒントを与えてくれる。
また、仮に退屈論を現代において本格的に展開する場合、退屈を感じる脳のメカニズムや、仮想を規定するコンピューター技術について述べる必要性を感じた。逆説的に、コンピューターは退屈するか、という問いを立てることで、動物や人間の仮想領域がその身体に由来するものであることを指摘できるかもしれない。そして希望という不確かな喜びは、その不確定性故にコンピューターには想定困難だとすると、コンピューターは希望も持てず退屈もせず、退屈を生み出しているメカニズムは完全に身体的かつ動物的だと論じられるかもしれない。
日本という国が、資本主義の成熟を通過して老いつつある今だからこそ、退屈について、コジューブやハイデガーとは全く異なった新たな視点から、私たちの哲学を立ち上げることができないだろうか?そろそろ、現代日本から生まれた哲学を、これが私達の哲学なのだと、胸を張って述べる必要があるのではないか。だからこそ私は、この本の結論に、<動物になること>ではなく、國分氏の言葉による、新たな概念による退屈への処方箋の言葉を聞きたいと感じた。それが、「自分らしく、自分だけの生き方のルールを見つけること」だと信じて。
 |
暇と退屈の倫理学 朝日出版社 |
 |
スピノザの方法 みすず書房 |