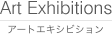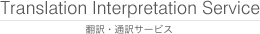渡辺真也
3.11の震災があった直後の3月15日、文化庁からの手紙が届き、ベルリン行きの奨学金を頂けることになった。その合格通知の日付は皮肉にも2012年3月11日付けで、あまりの偶然に驚き、手が震えた。その時私は、これは「日本がこんな大変な時だからこそ、お前は日本の為にも頑張って来い!」と言うメッセージなのだろう、そう理解した。
3.11の震災体験が私に与えた影響は大きく、今まで自身のテーマであった自己と他者の問題や、主体と客体の問題、さらに人間にとって幸福とか何か、そして魂とは何か、という根本的な問題を考え抜く契機となった。その後ベルリンに渡り、そこで体調を崩して入院に至る過程にて、いくつか重要と思われる体験をして、そこから考えることがあったので、この機会に書き記しておきたい。
私の身体は乗り物か?宇治野宗輝さんとの会話を通じて
2012年6月にベルリンのシャリテ病院に入院するまで私が一番考えていた問題は、魂とは何か、そして芸術とは単なる概念ではなく、魂を扱う領域なのではないか、ということだった。 発病する直前の私は、多くの人からの相談に乗っていた。将来の不安や生活など、多方面から相談してくる人たちが、日本人に限らず沢山いた。当時の私は皆の悩みを自分のものとして共有し、相談に乗ることはとても重要だと考えており、また国民の税金でベルリンに来させて頂いている国費留学生というある種の負い目もあってか、困っている人たちからの相談にはできるだけ乗ってあげたい、という思いから、毎日一時間ほど、様々な人からの相談に費やしていた。そういう状況の中で、「自己と他者」の区別が少しずつ曖昧になって来た部分が少なからずあったのだと思う。
入院する数週間前、友人のアーティストである宇治野宗輝さんの個展がベルリンのPSMギャラリーであり、私は文章を寄稿させて頂いた。
Ujino’s “Radio Activity” – A Parallel History of the Material Culture of 20th Century Japan
宇治野宗輝「Duet」に寄せて − 日本の伝統における想像的存在のリアリティ
個展オープン後、宇治野さんと二人で飲みながら、「ショーペンハウエルは自らの身体を客体として捉えていたんですよ」と宇治野さんに話した所、彼が48歳になり老化を体験する中で初めて、人間の体が乗り物であるということに気付いた、という話を披露してくれた。
機械に詳しい宇治野さんは、人間の体は車とよく似ていて、まず一番最初にパーツから痛んで行く、と話してくれた。例えば髪の毛が抜けて薄くなって行くのは、車に例えるとタイヤが摩耗するのと一緒、また目が悪くなるのは、ライトバルブが切れるのと同じで、体の柔らかいパーツ部分から先に壊れて行く。逆に筋肉や骨など車のシャーシに当たる部分は一生モノで、それほど簡単には壊れない。人間の体が乗り物だと気付いた時、自分の体をうまく乗りこなせるようになった、そう話してくれた宇治野さんに、とても世界観の広いアーティストだな、と感銘を受けた。
呼吸ができない!
宇治野さんからその話を聞いた二日後の夜のことだった。夜の1時半にベッドに入ってウトウトしている時、ふと宇治野さんの話を思い出して、こんなことを考えた。もしも宇治野さんの体が宇治野さんの魂の乗り物であるとした場合、その宇治野さんの体が知覚しているものを、私の魂は知覚することはできるだろうか?つまり、私の魂が私自身の体に乗っているのだとするのであれば、私の魂、そして意識の主体を、自分自身の身体を反映するのではなく、目の前にいる宇治野さんの身体を反映することは可能だろうか?つまり私の魂は、他者の身体の知覚を感じる事が可能だろうか、そんなことをふと考えた。
ではどうしたら、私の魂が宇治野さんの体の知覚を自分のものにできるのだろう?と少し集中力を高めて考えたその瞬間、私は呼吸ができなくなってしまった。呼吸ができなかったのは、ほんの3秒ほどだったが、明らかに自分の体が全く動いていない、そしておそらく眼球がひっくり返った状態にあることが理解できた。自分の呼吸が止まっている、つまり今まで無意識にしていた呼吸が完全にできなくなっている、そして自分の魂というのだろうか、知覚というのだろうか、意識だけがとてもクリアに存在していて、とても深く、はるか遠くに飛んで行ってしまっていることが理解できた。その意識が体と一切リンクしていないという状況が分かった時、凄まじい恐怖と苦しみを感じて、これはおかしい、まずいと思って、自分の体に魂を戻そうと試みた。すると私の魂は無事に身体に戻ることができたのだが、ちゃんと自分の身体と意識主体がフィットするかどうかを確かめようと手足を動かした所、その後一分間ほど身体が痺れたまま上手く動かすことができず、とても恐ろしかったのだが、その恐怖さえもどこか他人事に思える様な、不思議な感覚があった。その恐怖を和らげてくれたのは、ルームメイトがドアの向こう側で物音を立てながら話をしている音で、その時私は、ああ俺には周りの音が聴こえる、大丈夫だ、生きている、と実感した。時計を見たら、午前2時半ころだった。
その時感じたのは、聴覚は視覚以上に人間を現実世界に引き寄せる強い力がある、ということだった。それはテレビに例えると、映像が映らなくても音声だけ流れていれば、放送は続いていることは分かりそれほど不安にはならないが、逆に音声が無くなり映像のみになった場合、より強い不安が訪れることに似ていた。
ラマチャンドランのレクチャーと、私の手にあった髪の毛の触覚
この体験と前後して、私はカリフォルニア大学サンディエゴ校の神経科学研究所所長を務めるヴィラヤヌル・ラマチャンドランによるTEDのレクチャービデオを観た。
ラマチャンドランは存在しない腕(ファントム・アーム)の痛みを訴える患者を治療したことで有名だが、彼は、例えば左腕の無い人が、目の前の誰かが左手で何かをつかんだ時、自分の存在していないはずの左手がその触覚を自らのものとして知覚してしまう、つまり自らの皮膚感覚をなくした左腕のない人は、他者の左腕を見た時に、自らの左腕の皮膚からのフィードバックが存在しない為に、目の前にいる人の左腕の触覚を自分の腕のものだと誤認してしまうことから、「自己と他者」とを区別をしているのは皮膚感覚でしか無い、と神経科学的に結論づけた。
アジアの哲学は常に「自己は存在しない」と言うことをひたすら説いて来たが、それは「自己と他者」の間にニューロンネットワークが存在しており、他者への共感というものが既に自己の意識の中に組み込まれているからであり、今まで別物だと考えられていた科学とヒューマニティは、同じものとして論じることが可能だ、と述べた。そのレクチャーを観た私は大変感動し、ラマチャンドランはなんて優秀な学者なのだろう、と感心した。
それから数日後、ベルリン芸術大学大学院のゼミに参加した時のことである。大きな机を囲んで学生たち20人ほどが座ったのだが、私のちょうど向かいに座ったのが大柄なドイツ人の女性だった。その人は自分の手で金髪の髪の毛をクルクルといじる癖があったのだが、長時間に渡るゼミの最中、目の前で髪をずっといじっているその女性をぼーっと眺めていたら、彼女が右手で触っている髪の毛の感覚が自分の右手の指先に生まれて、とても驚いた。しかもその感覚は鮮明で、私自身の髪の毛よりも明らかに柔らかかった。それを体験した時に、俺はちょっと精神的に危険な所に来てしまったのだろうか?と思い、自己の意識を確立させている基盤の様なものが解体してしまったかの様な危機感を抱いた。
アルファベットのCが青く見える
当時の私は、できるだけ早くドイツ語をマスターしたいとの焦りから、ドイツ語を猛勉強していた。ゼミの日から2日後の午後、ドイツ語の本を読んでいると、突如アルファベットの「C」の文字だけが、青くにじんで見えるようになった。その感覚は、Cと言う「文字」に青を感じると言うよりも、Oという円環する文字の右端だけが切れた文字Cが青く見える、という感覚に近かった。ああ、これが共感覚と言うものなのか、と呑気に考えていて、もしかしたら私を含む普通の人間にもこういった共感覚的な才能があるのだけれど、普段はそれは隠れているだけなのかもしれない、と思った。
歩行困難となり、シャリテ病院に入院
その次の日のことである。朝目が覚めたら、歩けなくなっていた。まず、自分が何故歩けないかの理由が、よく分らなかった。とにかく目眩が酷く、自分がどこに居るのかは分かるのだけれど、何がどうなってるのかが、よく分からない。トイレまで歩いて行こうとしても、歩けないから、必死に這って行き、水を飲んでもすぐに吐いてしまうし、何が起こっているのか、よく分からない。一日休めば良くなるのかと思い、一日中寝ていたのだが、次の日も全く良くならず、症状は悪化した様だった。
なんとか友人に電話して、ベルリン最大手の大学病院シャリテに連れて行ってもらい、そのまま入院し、検査を受けた。検査を受けて最初の3日間ほどは原因が良く分からず、その間病状が良くならなかった為、もしかしたら私はもう元通りにはならないのかもしれない、と不安を抱いた。しかし結果が出ると病状はそれ程重症ではなく、左耳の前庭神経炎という神経の病気で、左耳の神経が痛んでしまった為、左耳の神経と繋がっている左目が固定できず、常に左目の眼球だけが右方向へと動いてしまい、その結果、自分の視野にあるスクリーンが常に右に動き続けてしまい、体のバランスを取ることができない為に歩行が困難になったということだった。またこの病気の原因も、ウイルスの可能性を指摘する医者と、もしくはただの過労だとする医者があり、その原因が未だによく分かっていない病気だ、とのことだった。
神経炎の痛みとその部位について
この神経炎の中で軽い痛みを感じた部位は、ドイツ語の勉強を集中して行っている時や、他者の問題を真剣に考えている時、さらに同時通訳をしているときに疲れる頭の部位と非常によく似ていた。感覚的なことしか言えないが、頭部左側の下の奥の辺りである。
少し話が逸れるが、2007年頃のニューヨークで、政府系の仕事をしているアメリカ人男性と、社会福祉系の仕事をしている日本人女性の同時通訳をしたことがある。アメリカ人の男性は非常に論理的な話をする弁護士タイプの人だったが、日本人女性の人は比較的感情を全面に出す人で、必ずしも論理的な話し方をする人ではなかった。アメリカ人男性は、この日本人女性と話が噛み合わずにちょっと困った様子だったが、私はあくまで通訳なので、とりあえず双方の言っていることを同時通訳した。彼女が「でも私、こうしたいんです!」と言ったときに、私は「No, I really want do it!」みたいに女性に乗り移った形で同時に通訳をしていたのだが、その通訳を1〜2時間やった日の夜の、あたかも自分の胸が膨らんで行く様な、自分の精神と体がフィットしていない様な不思議な感覚に陥り、寝られなくなってしまった。そのときに疲れていた頭の部位と、この病気になったときに痛みを感じた頭の部位が、良く似ていた。
ドイツの病院は最低限の治療だけしかせず、すぐに退院させる傾向がある。私は五日間入院して、まだ1人で階段の上り下りもできない状態で退院させられたのだが、病院からタクシーに乗り家へと向かう途中、目に入ってくる自然が本当に美しかった。また病院の食事でサラダが出てきた時、それは生き物である、という感覚が強烈にあり、食べるという行為が、生命体を自らの体の中に入れる行為として感じられた。病院の外は、生き物に囲まれた空間という感じで、自然は何故これ程までに素晴らしいのか、という圧倒的な感動があった。
ニーチェの言う「わたし」とは誰か?
入院する数週間前、友人のアーティスト、パオロ・キアセラとの会話の流れの中で、私が何気なく「ニーチェは発狂してしまったけれど」と話した際、パオロは「いや、ニーチェは発狂していないと思う」と力強く答えたことがあり、そうか、そんな風に考える人もいるんだなぁ、と感心したことがあった。パオロは入院中の私を見舞いに来てくれたこともあり、ベッドの上に横たわりながら、私はニーチェは一体何を考えて、どういう状態に至ったのだろう?と考えた。
(以下は私が字幕を担当したパオロ・キアセラのビデオアート作品「スープ皿の聖母)
退院後三週間ほど経過し、発病から一ヶ月程して本が読めるまでに回復した後の私は、ソクラテスとプラトンの話す魂の問題や、ニーチェが言っている「わたし(ich)」という考え方が、非常に良く理解できる様になった。そしてニーチェは発狂したのではなく、「わたし(ich)」という言葉は単なる一般名詞でしか無い、と言うことに最初に気付いた西洋近代人ではないか?と考えるに至った。
例えばニーチェは、音楽家ワーグナーの妻コジマ・ヴァーグナー宛の手紙の中で、「私が人間であるというのは偏見です。…私はインドに居たころは仏陀でしたし、ギリシアではディオニュソスでした。…アレクサンドロス大王とカエサルは私の化身ですし、ヴォルテールとナポレオンだったこともあります。…リヒャルト・ヴァーグナーだったことがあるような気もしないではありません。…十字架にかけられたこともあります。…愛しのアリアドネへ、ディオニュソスより」と書いている。
これを持ってニーチェは発狂した、と考える人は少なくないだろう。しかし私は、ニーチェがここで述べている「わたし」とはニーチェ自身ではなく、「わたし」とはただ単に一般名詞としての入れ物に過ぎず、その一般名詞である「わたし」という言葉を用いて、歴史上の出来事を述べたものだと考える様になった。
たとえば私、渡辺真也が博士号を取ったとしよう。すると私は「博士」になる。もしも鈴木さんが博士号を取れば、鈴木さんも「博士」になる。そうすると、渡辺も「博士」だし、鈴木も「博士」だから、「博士は今、ベルリンにいます」という文章と、「博士は今、東京にいます」という文章は矛盾しないことになる。つまり、博士という言葉は一般名詞に過ぎないから、「博士は相対性理論を立ち上げた」と「博士は文化人類学を立ち上げた」という文章は、どこかの博士がやったことである限り、何ら矛盾は無い。
ニーチェが気付いたのは、「わたし(ich)」とは、今ここに居て、この身体が考えている「わたし」であるフリードリヒ・ニーチェに限定されるものでは無い、そして「わたし (ich)」という言葉の意味さえも、他者との共有により初めて成立するのであり、皆が自らの自由意志に則って使っていると思い込んでいる一般名詞「わたし」が従える述語は、実は全て自然の摂理の結果でしか無いことを、彼独特の哲学的言い回しで表現したものなのだろう。 すると、一般名詞でしか無い「わたし」は、インドに居たころは仏陀、ギリシアではディオニュソスだったり、アレクサンドロス大王とカエサルや、ヴォルテールとナポレオンだったとしても矛盾が無い。
さらにニーチェは、「わたし」が「人間であるというのは偏見です」と、私に乗り移っている魂の領域さえ拡大してしまっている。ガートルード・シュタインが、時系列の違いにおける主語の扱い方を表現のテーマとして扱い始めたのは20世紀以降のことで、ニーチェの登場は早過ぎたのだろう。だからこそ、彼の言っていることを理解できない周りの人たちは、彼が発狂したと早とちりしてしまったのではないか、そう私は考える様になった。
自由意志と決定論
ニーチェにとって「わたし」とは、入れ物の様な言葉だったと私は考えるが、近代という時代は、「私はこう思う」や「私はこうしたい」といった、「わたし」の意思、つまり「自由意志」に則って物事を決定しているのだと考えてきた。しかし脳科学が発達するに従い、私たちが決定したと意識しているものは、実は無意識の集積の結果であり、そこに自由意志は存在しない、という考えに傾きつつある。言わば自由意思と呼ばれるものは、意識主体である「わたし」をフィクションとして生み出し、時系列を司っているものに過ぎない。
自由意志論者は、物事の結果について、「これは必然ではなく偶然だ」と考えるが、決定論者は「これは偶然ではなく必然だ」と考える。全ての事象は既に決定済み(決定論)であり、自由意志という表象像・言葉は単なる身体の動きに過ぎないとして、自由意志の存在を否定した哲学者スピノザは、こんな言葉を残している。「自分は、自分の精神の自由な決意にしたがって、何かをしゃべったり、黙っていたり、その他等々のことをしていると信じているものは、目を開けながら夢を見ているにちがいないのである」(スピノザ『エチカ』第三部定理2の備考)
例えば、”The pen falls.”という英文では、落下する主体であるペンに、意思はもちろん存在しない。Fallという動詞は自動詞で、あくまで自由意志が存在しない物理法則(エントロピーの法則)を表記したものに過ぎず、落下する「ペン」は客体を取らない。そしてスピノザの述べる決定論に従うと、「わたし」という主体が従える他動詞も、自由意志ではなく、ペンと同じく物理法則に従っていると考えることができる。
物理学者のシュレーディンガーは、自我の意識は常に単数形の経験であり、呼吸する私という意識主体は宇宙と同一化(梵我一如)している為、そこに自由意志は存在しない、つまり私を生み出す意識を単一の存在と捉えて「わたし」と呼ばれるものは、個体の記憶を集めて絵を描く土台の生地である、と考えた。人間を含む宇宙(外界)は、宇宙のエントロピー法則に従って動いているが、その宇宙を「わたし」の視点から眺めた時、常に「わたし」が中心となった宇宙として捉えられる。そこで絵を書く土台の生地として「わたし」と呼ばれるものが現れ、その「わたし」は「自由意志」に則って行動している、という仮想が成立する。
私という主体は、キリスト教世界の神の意思と矛盾せず、あくまでその代弁だとして発達した側面があるが、デカルト的な疑うことができない自己の存在(コギト)、言い換えれば自己愛から開始してしまった場合、それは必然的に他者と敵対してしまい、また仮に他者の存在から自己を規定しようと試みると、それは暴力的他者を生み出してしまう。
一方、仏教の縁起の思想では、自己は他者との関係の中で初めて存在可能となるから、これらの問題を無矛盾に解決できる。またもしも考える自己を存在として宇宙の中心に据え、そこから思考を開始するのではなく、宇宙の物理法則に従う人間である「わたし」を他者との関係(縁起)の中で捉えることができれば、「わたし」と「自由意思」を中心とした宇宙から、宇宙エントロピーに従った「わたし」と「決定論」に従う人間生活へと移り変わることになるだろう。
近代国民国家と民主主義、自己責任論を乗り越えることは可能か?
また自己愛に基づく自己規定の延長線上に、言語や宗教などによって分断されたネーションがあるが、自己の存在から開始することを回避することができれば、その延長線上にあるフィクションとしてのネーションが解体し、近代国民国家の病である敵対概念、つまり敵対する他国という概念を乗り越え、戦争を揚棄できるかもしれない。その場合、ネーション規定である憲法を、宇宙エントロピーに従ったグローバル自然法の下に位置づけることで、全てのネーションを一つの自然法則の下にまとめることが可能だろう。
またこの一神教の中で発達した、主体概念と自由意志に基づく政治体制が現行の民主主義だが、自由意志に基づいた場合、あなたは自由に意思決定できたはずだから、選択を間違えた場合、あなたには責任が伴うはずだと、という議論が生まれ、自己責任が問われることになる。しかし、そもそも民主主義が成立する前提である完全情報は成立し得ないし、また責任とは、基本的に他者や環境を抜きにしては語ることはできない。もしも自由意志に基づかない宇宙のエントロピーに従った意思決定システムを確立することができれば、自己責任という概念ではなく、その結果を導いた環境を修正することが人類共通の目的になるだろう。
一神論と多神教から考える自由意志と決定論
決定論を唱えたスピノザは汎神論者だったが、意外にも一神教と多神教とは矛盾しない。一神教の神に対する信仰のベクトルが複数になったものが多神教であり、また自由意志と決定論は、一神教と多神教における宇宙の切り取り方と相関関係がある。
一神教的な自由意志は、ただ単に「私が思う」という箇所だけをクローズアップして切り取っている。例えば、「私は今日スパゲティが食べたいから、私はスパゲティを食べに行く」のであり、それは私の自由意志である、といった具合に。しかし、決定論から考えた場合、動物である人間は、ネゲントロピーを摂取することで体内のエントロピー増大を相殺して定常状態を保っているが、これは自由意志ではなく物理法則に従っている、だからこそ人間は空腹を感じた時に、自分の経済的な状況や周りの環境が許す限りで、最良と思われるものを無意識的が決定し、その結果である「スパゲティを食べに行く」という行為を、意識が「自由意志」だと考えているに過ぎない、と考える。
つまり、「私はスパゲッティを食べた」という部分だけを自由意志として切り取るのは、一つの神を信仰する一神教における自己と外部との直線的な構図を、主語が述語を従えるというインド・ヨーロッパ語族の文法によって表しているに過ぎない。しかし、その自己という顕在意識を決定しているのが無意識に働きかけている環境であり、その自己と環境のベクトルは、自己を包み込む形で放射状に広がっているが、これは一神教の神に対する信仰のベクトルが複数化した多神教における信仰のベクトルと一致する。(自己と環境とを放射状に繋いだ場合、その自己における決定要因は、知覚情報の総和と一致するだろう。この環境と自らの行動について説いたのが、仏教の行(ぎょう)、つまりシャンカラ(saṅkhāra =formations)なのだろう。)
まとめると、一神教が主体と自由意志という発想に由来するのであれば、一神教の崇拝の対象が複数化したものである多神教は、環境が自らの行動を決定すると考える決定論と一致する。つまり一神教は自己を宇宙の中心に据えて自由意志を捉えるが、多神教では宇宙の中に自己を捉えることから決定論となる。
呼吸を意味する動詞と魂の関係について
またこの一神教の構造は、主語である「わたし」が従える動詞や、動詞とその格、さらに自動詞と他動詞の関係とも繋がって来る。ドイツ語で呼吸のことをatmenと言うが、これはサンスクリット語にて呼吸を意味するアートマンに由来する。バラモン教のヴェーダにて、アートマンは自我を表す術語になり、転じてアートマンは生気、生命原理、霊魂、自己を意味する様になり、ウパニシャット哲学では梵我一如として宇宙と統一された。またゲルマン系の英語には、「呼吸」を意味するサンスクリット語のasmiから、amやisなどのbe動詞(呼吸をするもの)が発生した。
また人が死ぬと呼吸が止まることから、ギリシャ語で呼吸を意味する動詞プシュケンが名詞化することで、魂を意味するプシュケーという言葉が生まれた。さらにギリシャ人たちは、魂とは天上の世界から肉体という墓穴へと堕落したものであり、その魂を清める方法が、ムーサの女神たちが司る歌、音楽、ダンス、詩、文芸であり、さらにその技術ムーシケーだとしたが、このムーサからミュージアムという言葉が、さらにムーシケーからミュージックという言葉が派生した。
興味深いのは、ドイツ語のbe動詞に相当する動詞sein(存在)で結んだ「AはBだ」の構文では、主語のAだけでなく述語のBも主格になる点だ。つまり主語「わたし」と述語(身体の外部)がイコールの関係で繋がれる。すると魂とは、呼吸をするもの、すなわち体の内部と外部を繋ぐ手段、言わばホメオスタシス(生体恒常性)と言えるかもしれない。
この呼吸をする「わたし(Ich, I)」は、呼吸という動詞を中間に据えることで、述語である身体の外部、つまり宇宙と繋がることが可能となるのだが、この発達を遂げたインド・ヨーロッパ語族は、アートマン(=真我、呼吸)は宇宙原理ブラフマンと一致すると考えたウパニシャッド哲学から出発しているのではないだろうか。比較神話学者のジョルジュ・デュメジルは、インドの叙事詩『マハーバーラタ』と北欧神話『エッダ』の間にある調和の豊富さと一貫性は、インド・ヨーロッパ語族の一部においてその拡散以前に既に形成されていたに違いないとし、そのルーツをゾロアスター教の影響を深く受けていないスキタイ人の末裔オセット人に求めているが、そこに位置するのが奥義書ウパニシャッドなのかもしれない。
またウパニシャッドには、自己(you are that)を意味する言葉に、Tat Tvam Asi(タト・トヴァム・アスィ)というサンスクリット語がある。ベルリン大学に留学していた旧東京帝大教授の坪井九馬三は、日本語の「たま(魂)」は外来語であり、その語源は「アートマン」であるという自説を展開し、同志社大学日本古代文学名誉教授の土橋寛が自著『日本語に探る古代信仰』においてその説を支持したそうだが、私は、このタト・トヴァム・アスィが、日本語の魂(たましい)の語源ではないか?と考えている。
主語の概念が発達していないウラル=アルタイ語圏の哲学者たちが、インド・ゲルマン族とは異なる方法で世界を眺めたり、異なる道を歩く可能性について指摘したのは、やはりニーチェだった。あたかもゴッホの様に、ニーチェもまた、西欧近代人としての視点から逃れるべく、主体を成立させる神の死を宣告した後に、「わたし」の存在しない世界を夢見て、実践したのだろう。一神教と自由意志、そして「わたし」という主語から逃れられない西洋世界はあたかも、言語体系に主語さえ存在せず、翻訳概念である主体としての「わたし」という主語さえ確立し辛い東洋世界における日本と、鏡合わせの関係にある気がしてならない。
追記:ニーチェは、コジマに例の手紙を出す数日前に、トリノの広場で鞭打たれる馬を守ろうとしてその首を抱きしめながら泣き崩れた、という逸話がある。また打たれている犬を見たピタゴラスは、「止めてくれ、これは私の友人の魂だ、声でわかる」と話したと言われる。私は偶然にもクレタ島にて、このニーチェとピタゴラスと同じ様な、魂の経験をすることになった。
関連記事: 「ピタゴラスと松澤宥の魂に出会う旅 - ゼウスの生まれ育ったクレタ島プシクロの洞窟を訪ねて」
協力:林友深(テープ起こし)